雷帝に欠けていたものは?
アンカラでのティムールとの直接対決で捕虜となり、表舞台から忽然と消えることになった雷帝バヤズィト1世の敗戦は、歴史的には必然でしょう。余りにも好戦的で自信に満ち溢れたバヤズィトという人物が、この時点での決戦を忌避するとは思えないからです。しかし彼がもう少し堅実で慎重な性格だったならば、ひょっとしたら歴史は大きく変わっていたかもしれません。
重要なのは、バヤズィトがティムールより遥かに若い点です。両者が最初に接触を持ったのはアンカラの戦いの10年近く前に遡り、この時ティムールは領土協定を持ちかけています。これにバヤズィトが応じていたならば東方遠征は繰り上げられたはずであり、直接対決はなかったかもしれません。なぜならティムールの寿命はバヤズィトを破った後、3年を経ずして尽きているからです。バヤズィトがコンスタンティノープルを落としてから、どちらに向かうつもりだったのかは想像の域を出ませんが、後継者たち同様ヨーロッパを目指したなら無論のこと、東を志向したとしてもマムルーク朝を屈服させるのが先決ですからね。ティムールのモンゴル高原制圧は容易かったでしょうが、明となると話は別です。広大なうえに、これまた傑出した軍事的才能を持つ永楽帝が相手です。おそらく長江までの制圧が限界で、明の根拠地江南を前にしてティムールは陣没することでしょう。マムルーク朝を倒したバヤズィトが相まみえるのは、カリスマを失い後継者の座をめぐって諸王子が争うティムール朝です。内部抗争を利用しての勢力拡大は、さほど難しくないはずです。つまりバヤズィトが最も念頭に置くべきは、彼が二回りも若いというティムールにはどうすることもできない事実だったと。残された時間を考えると、バヤズィトは性急すぎたのです。
バヤズィトの時代、ヨーロッパでは宗教改革の先駆的活動も始まってカトリック教会の権威は揺らぎ、また神聖ローマ帝国は封建社会の頂点という立場を失っていました。イタリアの都市国家は教皇派と皇帝派に分かれて争い、神聖ローマ帝国に代わって主導権を握ったフランスはイングランドとの百年戦争真っ只中、また黒死病(ペスト)の流行による疲弊はヨーロッパ全土に及んでいます。実際それでも催されたオスマンに対する十字軍は、1396年ニコポリスの戦いでバヤズィトに粉砕されており、さらなる大規模な十字軍を起こせたか疑問です。拡張期のオスマン朝歴代スルタンには、バヤズィトほどではないにせよ軍事に長じた人物が多いですから、最盛期を築いた大帝スレイマン1世が登場する前に西アジアからヨーロッパの大半を支配する世界帝国になっていた可能性がないとは言い切れません。しかしバヤズィトに徳川家康のような自己抑制心と忍耐力を求めても、やはりそれはないものねだりだったということになるでしょうね。全能の神アッラーの加護は精力的に異教徒との戦いを進めてきた我こそにあり、同胞を殺戮してきたティムールにはないと信じていたと。そのティムールに例え一時的にせよひれ伏すなど、誇り高い彼には到底できなかったのでしょう。
| 新・人と歴史 拡大版 25 オスマン帝国の栄光とスレイマン大帝 [ 三橋 冨治男 ]価格:1980円 (2025/7/16 23:53時点) 感想(1件) |







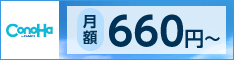
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません