タメルラング vs 雷帝
1402年7月20日、アナトリア半島中部アンカラ近郊チュブク草原においてオスマン朝のスルタン、バヤズィト1世軍と大アミールであるティムール率いるティムール朝軍が激突しました。所謂アンカラの戦いです。結果はティムールの完勝に終わってバヤズィトは捕らわれの身となり、オスマン朝は一時滅亡の危機に瀕することになります。
人類が戦争に明け暮れた近代以前には、洋の東西を問わず傑出した軍事的才能を備えた名将が引きも切らずに現れましたが、天才と言えるほどの存在となると限られます。しかしティムールをその中に入れることには、まず異論はないと思われます。バルラス部の傍流という大した後ろ盾のない出自でありながら最盛期のモンゴル帝国西半分に近い広大な版図を一代で征服した事実が、その天才的軍略と智謀を証明しています。
いっぽうのバヤズィトも雷帝と恐れられた英雄です。コソボの戦いで父ムラト1世が不慮の死を遂げた後、弟たちを粛清して迅速に権力を掌握、ブルガリア・セルビアに加えてバルカン半島とアナトリアの大部分を制圧してビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを陥落寸前にまで追い込んでいました。
歴史としてバヤズィトの決定的敗北を知っている現代人としては、彼をティムールと同列に扱う向きは皆無でしょう。しかし当時の勢いには甲乙つけ難いものがあり、周辺諸勢力は近い将来の激突が必至と思われていた両雄の対決を、固唾を吞んで見守っていたことでしょう。また時節を味方につけていたなら、バヤズィトが勝っていた可能性もあったのではないでしょうか。
勝敗を分けたのは、彼我の実力を客観的に評価できていたかどうかではないかと思います。ティムールは当初、バヤズィトに領土協定を持ちかけています。これはティムールの目が、かなり早い段階から東に向けられていたことを示唆します。チンギス・カンの後継者としてその故地北元を回復し、さらには明を滅ぼしてモンゴル帝国を復活させるためには西方の安定が重要であり、飛ぶ鳥落とす勢いのバヤズィトと戦いたくはなかったのではと思うのです。ところがバヤズィトの好戦的な態度を危険と判断、バヤズィトに征服されたベイリク諸国の要望に応えるかたちで遠征に踏み切ったということではないでしょうか。
対するバヤズィトには、やや自信過剰な面が見受けられます。おそらくティムール何するものぞという自負心が冷静な分析の妨げになったのでしょう。もしかしたらティムールはマムルーク朝の打倒を優先していると判断していたかもしれません。だとするならば、コンスタンティノープルを落としてから対決の準備にかかっても遅くはないと。そうでなく背後を突かれるかたちになっても問題ないと考えていたとすれば、明らかにティムールを過小評価していたことになります。豈図らんや、いざ対決へと舵を切ったティムールの進軍速度は余りに早く、バヤズィトはコンスタンティノープルの包囲を解いて迎撃のためアナトリアへ向かうことになります。ブルサで急遽軍を編成してアンカラまで駆けつけたバヤズィトの機動力も、さすがに「稲妻」の異名を持つ迅速さではありますが、やはり準備が万端とは言えない状態だったのは確かでしょう。老練で経験豊富なティムールに比べると、バヤズィトは若かったと言わざるを得ません。「稲妻」がタメルラング(跛者のティムール)に機先を制される結果になったのは、なんとも皮肉です。
両軍の兵力には諸説ありますが、ティムール軍が大きく上回っていたのは間違いないようです。バヤズィトは決して猪武者ではなく、決戦に至るまで地の利を生かして数的劣勢を覆す駆け引きが行われていました。バヤズィトは当初、アンカラに迫るティムール軍を高所から攻撃する作戦でしたが、斥候の報告から予想される進路に基づきアンカラに守備隊を残して森林地帯に布陣します。ティムール騎兵の機動力を削ぐ作戦であるのは明らかで、これは極めて理にかなっています。しかしティムールは大きく迂回してバヤズィトを出し抜くかたちでアンカラを包囲してしまうのです。ティムール自身にとっては外征ですが、従軍しているベイリクたちには勝手知ったる土地です。彼らから得られる情報を最大限活用したということでしょう。裏をかかれたバヤズィトはアンカラ救援のため、ティムール軍が待ち構える平原での決戦を余儀なくされたのです。やはり用兵においてティムールに一日の長があったということです。しかし強行軍で到着したバヤズィトの軍勢は、想定外の方角に現れてティムールを驚かせます。ここで間髪入れず攻撃しなかったことで千載一遇のチャンスを失ったという意見がありますが、疲労困憊した兵に休息が必要との判断ならば間違いとは思いません。
激戦の帰趨を決したのは、オスマン軍に従っていたベイリクの寝返りでした。その反面バヤズィトに服従していたセルビア貴族の軍勢はキリスト教徒であり、彼らにとってはオスマンもティムールも異教徒ですから、戦況が不利となれば早々に逃げ帰ってもおかしくところで最後まで奮戦しています。このことを考えるとバヤズィトは単なる好戦的な征服者ではなく、キリスト教徒にも畏敬の念を覚えさせるほどのカリスマだったと想像します。しかし同時代にティムールというさらなるカリスマが、同じイスラム世界にいたことが彼の不運だったと言えるでしょう。
| ティムール 草原とオアシスの覇者/久保一之【1000円以上送料無料】価格:880円 (2025/7/16 23:50時点) 感想(0件) |







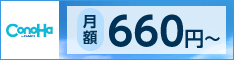
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません