海道一から天下一へ その19
このころ奥州では、伊達政宗が苦しい立場に置かれていました。父輝宗横死後各地で反伊達の動きが顕在化したことが佐竹・蘆名連合の攻勢を呼び、さらに出羽南部をほぼ制圧した最上義光も伊達領を窺っていたのです。そこで政宗は関東管領北条氏政に援助を求めることになります。
利家、北陸へ
家康の盟友前田利家は、家康の副官として畿内の軍事を統括してきましたが、国持ではありませんでした。与えられたとはいっても、それはあくまで軍事管轄権だったのです。そこで家康は利家に加賀・能登を与えることにします。鳴りを潜めているとはいえ、依然越後の上杉景勝を警戒している家康は、景勝に無言の圧力を加えようとの算段でした。もちろん論功行賞ですが、畿内の軍事管轄権を利家から引き剝がして自らの手中に収めるためでもありました。これに対して利家は抗いませんでした。家康の天下静謐への思いに共感するとともにその器量を認めていた利家は、家康の腹心として新たな世を切り開くことに情熱を傾けていたのです。
家康全国に検地を号令
幕府に敵対する勢力がなくなったことから、家康は納められるべき正確な年貢量を把握するため全国に丈量検地を命じます。それに伴い従来の貫高制から石高制に改めることにします。貨幣を自給できないうえに鐚銭の氾濫もあって銭での取引が嫌われる傾向にあり、生産量が激増した銀や米が取って代わりつつある実情を反映したものでした。
顕如が京に帰還
京復帰をめぐる本願寺顕如と長男教如の対立は深まるばかりで収拾がつかず、遂に顕如は自らに近い坊官とともに門徒を引き連れ京に向かいます。故地の山科を与えられた彼らは早速再建に取り掛かりますが、石垣や濠の設置は認められませんでした。幕府としては本願寺を京に取り込んだうえで、城塞化して寺内町を形成することのないよう目を光らすつもりだったのです。
いっぽうの教如はその後も大坂を退去せずに居座っていました。彼は自派の坊官を各地に派遣して援助を求め、勢力を回復しようと図ったのです。
秀康、小早川の養子に
かねてより家康の次男秀康を小早川隆景の養子に迎えることを画策して各方面から根回ししていた木下秀吉は、九州平定戦で隆景が家康と同陣しているうちに話をまとめてしまおうと隆景の説得に本腰を入れていました。当初隆景は、毛利輝元を憚って難色を示していました。あくまで本家である毛利を立てる意識が強い隆景は、あらぬ疑念を輝元に抱かせたくなかったのです。しかし秀吉は、足利義昭を奉じてあからさまに対決した輝元に対する家康の警戒心は一朝一夕に緩むものではなく、この先も冷遇されるであろうこと、そんな毛利を守るためには幕府内に強固な足場を築く必要があり、秀康に小早川を継がせるのが最上の策であると力説、遂に隆景も承諾します。これには隆景の兄吉川元春とその嫡男元長が、九州で相次ぎ病死したことも影響していました。後を継いだ広家も優れた武勇の持ち主でしたが何分まだ若く、輝元と家康の関係をうまく取り持つのは荷が重いと思われたからです。こうして隆景自ら家康に秀康を乞う形で養子縁組が決まります。家康としても、正室築山殿が承認しないゆえ認知することができない秀康を、半ば飼い殺しにするよりも遥かに有用と考えたのです。
| 近世初期の検地と農民 [ 速水融 ]価格:6050円 (2025/5/17 14:04時点) 感想(0件) |




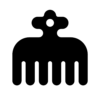
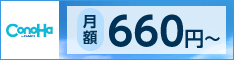
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません