海道一から天下一へ その20
本願寺顕如の京復帰後も大阪を離れず策動していた長男教如も、近衛前久の再三にわたる説得をようやく聞き入れて退去します。しかし顕如のもとには赴かず、各地の門徒を頼って転々とします。依然として支持者を増やし顕如に対抗しようと考えていたのです。
信康と北条の接近
徳川家康の嫡男信康は、自らの処遇に不満を持っていました。武勇に優れるにもかかわらず、西国平定戦から蚊帳の外に置かれて駿河に留め置かれていたからです。もちろんそれが北条・上杉に対する備えであることは重々わかっていましたが、鬱積した憤懣を持て余して家臣や領民にぶつけるようになります。そのいっぽうで正室の実家である北条との関係は非常に良好でした。義兄弟に当たる北条氏直との交流が深まるにつれ、信康の心中には一族内の争いが皆無な北条の家風およびその先進的な領国経営を憧憬するようになります。これには母築山殿と家康との関係が冷え込んで久しく、その反動からか築山殿の愛情が全て信康に注がれていたという事情がありました。なにかと今川の血筋を鼻にかける築山殿を家康は快く思っておらず、義元を憚って自重していた女好きも、その枷が外れてからは転戦を重ねる身でありながらも盛んになっていました。不遇を嘆く母を間近で見続けたことが、父に対する反発を増幅していたのです。また、松平家も同族内での抗争を繰り返してきた歴史があり、これは戦国の世では当たり前のことでした。ところが北条においては当代に限らず始祖早雲以来100年近く家中の諍いがないという稀有な存在です。この事実が信康を北条に接近させる大きな動機になっていたのです。
窮地の伊達
奥州の伊達政宗は厳しい局面に立たされていました。会津の蘆名は盛氏の死後を継いだ盛隆が男色のもつれで不慮の死を遂げ、その子亀王丸も夭折したため同盟者佐竹義重の次男義広が当主となっており、事実上義重の影響下にありました。南奥諸勢力の糾合に成功した義重は本格的に攻勢を開始、政宗はこの防戦に追われます。さらに出羽の最上義光もこれに乗じて伊達領を浸食、政宗は両面作戦を強いられていたのです。そこで政宗はまず、かねてから接近を図っていた北条に援助を要請します。和睦したとはいえ佐竹と北条は宿敵であり、北条が大軍を催せば佐竹はこれに対処せざるを得ません。さらに政宗は越後の上杉景勝にも誘いをかけて義光を牽制し、窮地を脱しようと試みたのです。
北条と上杉の反応
伊達の要請を受けた北条では、当主氏直は慎重な姿勢を見せます。幕府の斡旋で和睦した佐竹を攻めるとなると、あらぬ疑いを向けられる恐れがあると考えました。家康の婿である氏直としては幕府を刺激することは避けたかったのです。これに対して氏直の父氏政は積極的でした。奥州探題を自認する伊達が、奥州を騒がす佐竹の討伐を関東管領たる北条に要請したもので大義があり、私闘には当たらないとしました。氏政としては和睦したとはいえ佐竹は目の上の瘤であり、念願の関東完全制覇を果たす絶好機と捉えたのです。氏政の弟では、今川の人質時代から家康と親交のあった氏規が氏直に同調するものの、氏照・氏邦は氏政を支持します。家督は譲ったとはいえ氏政は関東管領であり、家中での発言力は依然として強いものがありました。また武闘派の氏照・氏邦の存在もあって氏直は対応に苦慮し、結局伊達との同盟に引きずられていくことになります。
いっぽうの上杉は躊躇しませんでした。というのも、大宝寺氏への影響力を行使して得ていた庄内地方の利権を最上に奪われていたからです。景勝は本条繫長と、庄内から逃れていた繫長の実子大宝寺義勝に出陣を命じるとともに、直江兼続にも後詰として向かわせることにします。こうして奥州の争乱が飛び火し、東国は俄かに騒がしくなるのです。




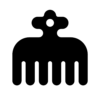
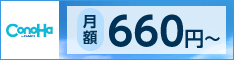
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません