決闘の日
4月13日は「決闘の日」です。これは宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の決闘が行われたことに因んでいますが、その詳細については不明な点が多く、確かなのは小次郎が単身で立ち合いに臨み武蔵に敗れたことだけです。
また時期についても武蔵が18あるいは19歳だった慶長6、7年(1601,2年)と、29歳の慶長17年(1612年)に分かれます。二天一流に伝わる武蔵伝記の中で最も著名な『二天記』における記述から慶長17年4月13日が一般的になっただけで、特に信頼性が高いわけではないのです。
しかし日付はともかく、10年の隔たりは大きいですよね。武蔵の剣名を轟かせた吉岡一門との対決が21歳の時とされているので尚更です。武蔵が13歳を皮切りとして数々の決闘に勝利してきたとはいえ、巌流島が殊更有名なのを考えると、やはり吉岡一門に勝利した後とするほうがしっくりきます。武蔵の自著『五輪書』に、29歳までに60余回の勝負を行い無敗とあることからも、小次郎との対決を一つの区切りと見ていたことが窺えます。ただし無想権之助や高田又兵衛と立ち合ったとされるのはそれ以降のことなので、これをどう解釈するべきでしょうか。真剣勝負(命の取り合いという意味での)はやめたという意味なのか、もしかしたら負けたから言及しなかっただけという可能性もありますしね。武蔵という人は『五輪書』を読んでも勝つことに徹する合理主義者という感が強く他流派に批判的な面もあり、剣術はあくまで相手を倒す武術であって人間としての高みを目指すところまで昇華してはいないように思えます。武蔵が史上最強の剣豪候補筆頭にしばしば挙げられるのは、そのマキャベリスト的側面を考えると納得できることではあります。
いっぽうの小次郎は武蔵以上に謎の部分が多く実像はわからず、はっきりしているのは名の知られた兵法者だったということだけです。『二天記』に18歳とあることから小説や映像作品では武蔵より年下に描かれますが、どうも眉唾です。武蔵の父とされる新免無二との因縁を記す資料が複数あることや、富田勢源あるいは鐘捲自斎の弟子とされていることから考えると、武蔵より年上と見るのが自然です。また史料によっては武蔵の弟子が勝負に関与していたとするものが複数あるのに対し、小次郎が単身だったことは一致しています。小次郎にも弟子はいたはずですが、勝負に際して姑息な手段を使う気がなかったことが窺えます。生意気で傲岸不遜な人物に描かれる小次郎ですが、実際にはかなりの境地に達した人格者だったのではと想像したりします。それが弟子同士のいざこざと無二との因縁が絡んでやむを得ず立ち合うことになってしまったのではないかと… さらには武蔵に敗れて廃れた吉岡一門と小次郎がともに京八流の流れを汲んでいることも関係しているかもしれません。船島と呼ばれていた決闘の地が小次郎の剣号とされる巌流島となった理由には、正々堂々と戦って倒れた小次郎を悼む声が多かったことがありそうです。
武蔵と小次郎を描いた作品は多く、すでに出尽くした感があります。そこで私としては老境にさしかかった小次郎を主人公にした作品を見てみたいんですよね。役所広司さんか渡辺謙さんを主役に迎えて。誰か映画化してくれないかなあ…
| 真説 巌流島 [ 浅野史拡 ]価格:2200円 (2025/4/12 13:25時点) 感想(0件) |





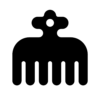

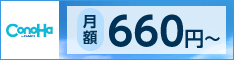
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません