海道一から天下一へ その17
幕府軍が八代を進発して水俣に入ったという報告を受けるに及んで、遂に島津義久は降伏する決意を固めます。もはや各地の国衆に対する統制も効かず、直率する家臣団がいかに精鋭とはいえ、これ以上の抵抗は国を亡ぼすと悟ったのです。主戦論の次弟義弘も不承不承ながら家中を乱す行動は避けるべきとこれに従い、九州の争乱は島津の完敗に終わるのです。
家康、義久を引見
義久は降伏の使者として、かつて幕府との折衝に当たった伊集院忠棟を派遣、家康は忠棟に対し義久自身が出水まで迎えに出るよう命じます。義久は出水に赴いて家康の到着を待つ間に剃髪して恭順の意を示します。その心中には、自らの命と引き換えに薩摩・大隅は確保したいという思いがありました。義久を引見した家康は、まるで見透かしたかのように二国の安堵を申し渡します。独自の気風を持つ島津領には誰を送り込んでも統治は困難と家康は判断していたのです。しかし、再び島津が反旗を翻すことを警戒する家康の胸中には策がありました。
佐土原開城
佐土原城に籠った島津家久は十河・長宗我部ら四国勢に囲まれていましたが、徹底抗戦の意志は変わらず攻められれば痛撃を与える覚悟で待ち構えていました。しかし義久は家久の抗戦によって薩摩・大隅安堵の約束を反故にされる危険性を感じて降伏するよう命じます。不服な家久はなおも抵抗するも、義久自らが軍勢を率いて接収する意思を示すと遂に屈服、幕府軍に城を明け渡します。これによって島津方の軍事行動は終息し、家康は具体的な戦後の仕置に入ることになります。
九州仕置
家康はまず薩摩を島津宗家に安堵しますが大隅は別でした。最後まで抵抗した家久に北半を与え、南半には重臣伊集院忠棟を充てたのです。開戦前から幕府との折衝に奔走した忠棟を義久と家久の間に配置したのは、島津家中の結束を綻ばせる意図からで、かつ約束を違えたことにはならないという理屈です。また日向にはかつての国主伊東祐兵を復帰させ飫肥城に置きます。大友義統には豊後一国を安堵、豊前は立花統虎に与えます。また肥前は龍造寺を廃して鍋島直茂のものとし、伊予の加藤光泰と讃岐の生駒親正をそれぞれ肥後と筑後に移します。さらに筑前に小早川隆景を配することで旧勢力に対する事実上の押えとします。島津の覇権を潰した家康は、それに乗じて復権を図ろうとする各地国衆の動きを警戒していました。
秀吉の野望
家康から筑前への国替えを打診された隆景は、当初難色を示していました。宗家を凌ぐ気のない隆景は毛利輝元に加増するべきと考えていたのです。これに対して腹心木下秀吉は、輝元に対する家康の疑心は変わっておらず、もし輝元が筑前を受け取れば本国を召し上げられてしまうと主張します。長門に隣接する筑前ならば、宗家に不測の事態が起きた場合にも迅速に対応できるため受けるべきと。隆景はこれに同意しますが、実は秀吉の真意は別のところにあったのです。
九州平定によって家康の権力基盤は盤石となり、天下静謐への流れには最早抗えないと秀吉は考えていました。そこで目をつけたのが朝鮮半島です。国内の戦乱が収まれば、領土拡大意欲が行き場を失うのは明らかです。これを外に向けさせ切り取ろうというのです。その橋頭堡として筑前は絶好であり、隆景の筑前入りは秀吉にとって渡りに船だったのです。
| 島津家久に学ぶ「軍法戦術に妙を得る仕事術」【電子書籍】[ 宮内露風 ]価格:329円 (2025/4/27 16:42時点) 感想(0件) |




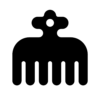
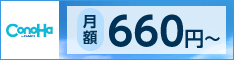
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません