海道一から天下一へ その18
九州を平定した徳川家康は、かねてから朝廷より打診されていた正二位内大臣への就任を受諾します。これまで諸勢力の反発を懼れて突出することを避けていましたが、将軍不在の幕府における権勢の確立は最早自他ともに認めるものであると判断したのです。実を手に入れた家康は、今後どのように名を獲得するかに腐心することになります。
家康の懸念
損害を最小限に抑えて島津を屈服させた家康ですが、ただ一つ想定外だった懸案が生起しました。それはキリシタンの数が予想を遥かに上回るものだったことです。家康は南蛮貿易を重要な財源と考え振興しており、キリシタンを禁じる気はありませんでした。しかしそれは彼らの目的が飽くまで通商にある限りのことです。この頃すでに海上の覇権はポルトガルからスペインに移り、さらにイギリスが急激に台頭してスペインに挑戦しようという状況です。対立が激化してこれらがもし通商のみに飽き足らず征服に舵を切った場合、キリシタンを尖兵に用いようとすることは想像に難くなく、これ以上のキリシタン増加は介入を招く原因となるでしょう。また国内においても家康が目指す政教分離は完成していません。かつて朝廷や幕府が苦しめられてきた寺社勢力が、再び政治に関与して増長するような事態は避けなければならず、その芽を摘んでおくことは必須です。そこで家康はまず、棚上げしていた大坂本願寺の京復帰に向けて動き出します。
本願寺の内紛
大坂本願寺門主顕如は家康から打診されていた京復帰に前向きでしたが、長男教如は強硬に反対していました。これは顕如の室如春尼が三男准如を偏愛していたことに危機感を覚えたこと、教如が寵愛していた側室如祐尼と如春尼の折り合いが悪かったことから後継者を巡っての争いに発展しており、坊官衆筆頭で奏者を務める下間氏一族も両派に分かれるなど対立が深まっていたことが結びついていたのです。本願寺の京復帰問題は、これに拍車をかける形になって教団内部の結束を緩ませることになります。
東の課題
西を押さえた家康の目が東に向くのは当然でした。上杉景勝は娘婿であり表面上幕府に敵対する態度は見せていませんが、没落した将軍足利義昭を匿ったという事実はすでに明らかで、その真意は測れません。上方の政局から距離を置いて領国経営に専心しているうえ謙信以来の尚武気風は健在と思われ、敵に回すと厄介です。また北条氏直も婿であり、その父氏政は嫡男信康の舅という二重の姻戚関係にあります。しかし関東管領としての北条をこのまま放置すれば、かつての鎌倉府のように幕府から半ば独立した政体として認めることになり、全国一元支配という家康の目的を阻む存在になります。さらに危険なのは両者が結託して立ちはだかる可能性です。元来犬猿の仲であるとはいえ、些細な利害の一致が大同団結に走らせないとは限りません。家康は両者の接近を防ぎつつ、如何にしてその勢力を削減していくかという難題に向き合うことになります。
| 宣教師とキリシタン 霊性と聖像のかたちを辿って (西南学院大学博物館研究叢書) [ 下園 知弥 ]価格:1100円 (2025/4/27 16:56時点) 感想(0件) |




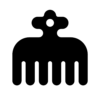
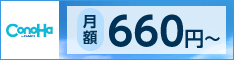
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません